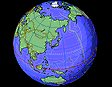 |
9.中央駅と水力ケーブルカー |
|
|
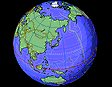 |
9.中央駅と水力ケーブルカー |
|
|
|
|
| ストラスブールは、EUの本会議場が置かれている人口25万人ほどの街ですが、近代トラム復活の街として知られています。
旧来のトラムといえば、日本の地方都市に残る路面電車と同じで、スピードは遅く、床が高くて乗り降りが不便で、自動車の通行の妨げになる等々、悪い部分ばかりが目立つ前時代的な乗り物でした。 事実ストラスブールでは、80km以上あったトラム網が全廃されていたそうです。 しかし1989年に地下鉄建設計画を撤回し、市中心部は自動車の乗り入れを制限して周縁部に格安の駐車場を設置したり、また道路の一部を自動車が走れない電車専用軌道にしてしまうなど、トラム優先施策を実施した上で、1994年に床が極端に低く加減速に優れた斬新な車両を導入して開業しました。 その結果、市街地の渋滞や路上駐車は減り、中心街は徒歩でショッピングを楽しむ人々で賑わうようになったということです。 ストラスブールのトラムについては、Le Tramが詳しいです。 |
 |
 |
| 市中心街クレペール広場と虹 | 斬新なトラム車両 |
|
トラムは大きく2路線に分けられ、モニュメント的なドーナツ屋根が設置された、市街中心部のクレペール広場で交差しています。 歩道と線路に境や段差はなく、トラムが来ないとき、人々は当たり前のように線路内を歩いています。 また自動車進入禁止の看板もあちこちに見られ、細い路地はトラムと歩行者の専用となっています。 古い街並みを抜けて走るため、細く曲がりくねった路地でも通り抜けられるよう、幾重にも節を連ねた連接構造の車両になっています。 実際には6つの節で、「短-長-短-長-短-長-短」と長短あわせて7つの車体を連ねています。 運転台のある先頭部を含め、短い車体には車輪がありますが、長い車体には車輪はなく、短い車体と車体の間に吊られている構造です。 また車輪はロングシート(車体内側に向かって座る横長の椅子)の下に納められているので、車輪の分の床をかさ上げする必要がなく、低い床面を実現しています。 |
 |
 |
 |
| ドーナツ屋根 | 自動車進入禁止エリア | 細く曲がりくねった路地 |
|
さて、前ページで謎かけをした国鉄中央駅とトラムの接続ですが、やはりありました。 中央駅正面の大きな広場には地下階が設けられ、地下1階の観光案内所や駐車場の更に下にトラムのホームがありました。 ちなみに地下駅はこの中央駅だけで、その前後は2・3分走った地上に停留場があります。 このようなトラム地下線は、ベルギー・ブリュッセルにもありました。 |
 |
 |
 |
| 中央駅地下トンネル | 中央地下駅 | 地下トンネル入口(北西) |
|
次に車両についてですが、ホーム自体も20〜30cm程度と低いですが、ホームと車両床面の段差はほとんどありません。 また扉は外側に開くスライドドアで開口部が大きく、車いすでも楽々乗り込んでいました。 車体側面は扉を含めてほとんどガラス張り状態で、イスやポールなどの配色と相まって、車内はとても明るい雰囲気です。 運転室も客室から丸見え状態でしたが、その入口部はちょうどいい凹みになっていて、絶好のカップルスペースとなっていました。 運転している真後ろでチュッチュされたら、運転に集中できないのでは・・・。 |
 |
 |
 |
| 段差のない大きなドア | 明るい車内 | 運転室 |
|
最後に運転台についてですが、椅子自体がエアサスペンションで支持されていて、腰への負担も考えられています。 フランスやスペインのバスもそうだったのですが、ヨーロッパの車両は運転する人のこともよく考えられています。 また運転台には左右にバックモニターが付いていて、後方のドアで人が挟まっていないか、などの確認ができるようになっています。 でも一番ビックリしたのがスイッチ類。 なんと椅子の肘掛けに付いているんです。 左側が加減速のレバー、右側がドア開閉関係のスイッチのようでした。 |
 |
 |
 |
| エアサス椅子 | バックモニター | 運転席 |
|
|
|
|
| ストラスブール市内見物 |
| << 3日目 |
|
5日目(準備中) >>
|
|
|
|
掲示板 |